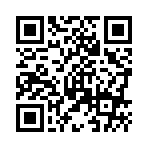2020年09月03日
明治を学ぶ19
明治19(1886)年3月、勅令として学術を極める目的で帝国大学令が出される。帝国大学設立。
内地に7校(七帝大:東京、京都、東北、九州、北海道、大阪、名古屋)、外地に2校(京城、台北)が設置された。
総称が「帝国大学」であった現在でも、「旧帝国大学」または「旧帝大」とも呼ばれていたりもしますね。
このときに京城-韓国と台北-台湾にも国立大学作っていたんだね。
「帝国主義」とは。政治・経済・軍事などの面で、他国の犠牲において自国の利益や領土を拡大しようとする思想や政策の事。この時代の欧米列強はこの考え方で日本もこれを目指さないと植民地にされてしまうと考えていた。
5月井上馨外相条約改正会議を5か国(英・蘭・仏・露・米)と秘密裏に始める。
10月24日、ノルマントン号事件。イギリス船籍の貨物船ノルマントン号が、横浜から神戸へ行く途中、和歌山沖で座礁沈没した。このとき外国人乗組員のみ助かり日本人乗客25名が全員死亡する不可解な状況が起こった。
日本中で船長の責任が問われたものの日英修好通商条約の治外法権で不問となり、船長らの人種差別的行為と不平等条約による領事裁判権に対する国民的反発が沸き起こった。
天草で関係することを書くとこのときのノルマントン号引き上げ事業に牛深町の宮川清一さんが参加されている。
おそらく漁師の潜水夫として呼ばれたのだろうが沈没地点だと思われる場所は深さ90メートルあったため人力では30メートル潜るのが限界だった。
明治20年4月22日、井上馨外相が5か国と条約改正に合意。しかし裁判に外国人判事を任用するなどの実質変わらない条約改正案の内容が公表されるとに反対運動が起こる。裏を返せば、まだ国としてなんの後ろ盾の力もない日本は条約改正したくてもできなかった。列強と対等に見られるため近代的な憲法が必要でした。
6月、伊藤博文ら「憲法草案」作り始める。
目指したものドイツ式立憲君主制。
伊藤以外の憲法草案のメンバー↓
井上毅(こわし・肥後)渡欧経験あり教育勅語草案にも参加。
伊藤巳代治(みよじ・肥前)憲法調査の為伊藤に随行。
金子堅太郎(筑前)岩倉使節団そのままハーバード卒。
8月、憲法草案完成、作った場所にちなみ「夏島草案」と呼ぶ。
9月、条約改正案に閣僚も反対し井上外相辞任せざる負えなくなった。
10月、条約改正案反対で民権運動が再燃。
12月、保安条例公布で民権運動派危険人物570人を東京から排除。
明治21年4月30日、憲法草案の審議の為、枢密院を設立。
内閣から独立した存在で直接天皇を補佐する諮問機関。初代枢密院議長に伊藤就任同時に総理辞任したため後任に黒田清隆(薩摩・幕末牛深へ来ていた)就任。
6月18日、枢密院憲法会議初日、伊藤は自分の考えを演説。
「ヨーロッパでは道徳的な基軸として宗教を持つが、我が国では宗教の力が弱く基軸とすべきは皇室あるのみ」と力説している。神道でもなく皇室だと言っているのは実質同じだと言ってもいいけどはっきり言うと皇室を中心とした皇室神道っていう分類になると思う。
10月、明治宮殿完成。(現在の皇居)表は和装、内は洋装。
11月、日墨(メキシコ)修好通商条約締結。初の完全対等条約。
明治22(1889)年2月11日、大日本帝国憲法発布。東アジア初近代憲法を持つ国になった。

出来たばかりの新しい皇居(明治宮殿で)発布。明治天皇から憲法を渡されている人は総理の黒田。

外務大臣を辞任した井上は黒田内閣になると農商務大臣へ復帰している。
大日本帝国憲法については大テーマなのでまた次の回へ。まだ国会開設までいけませんでしたねw
内地に7校(七帝大:東京、京都、東北、九州、北海道、大阪、名古屋)、外地に2校(京城、台北)が設置された。
総称が「帝国大学」であった現在でも、「旧帝国大学」または「旧帝大」とも呼ばれていたりもしますね。
このときに京城-韓国と台北-台湾にも国立大学作っていたんだね。
「帝国主義」とは。政治・経済・軍事などの面で、他国の犠牲において自国の利益や領土を拡大しようとする思想や政策の事。この時代の欧米列強はこの考え方で日本もこれを目指さないと植民地にされてしまうと考えていた。
5月井上馨外相条約改正会議を5か国(英・蘭・仏・露・米)と秘密裏に始める。
10月24日、ノルマントン号事件。イギリス船籍の貨物船ノルマントン号が、横浜から神戸へ行く途中、和歌山沖で座礁沈没した。このとき外国人乗組員のみ助かり日本人乗客25名が全員死亡する不可解な状況が起こった。
日本中で船長の責任が問われたものの日英修好通商条約の治外法権で不問となり、船長らの人種差別的行為と不平等条約による領事裁判権に対する国民的反発が沸き起こった。
天草で関係することを書くとこのときのノルマントン号引き上げ事業に牛深町の宮川清一さんが参加されている。
おそらく漁師の潜水夫として呼ばれたのだろうが沈没地点だと思われる場所は深さ90メートルあったため人力では30メートル潜るのが限界だった。
明治20年4月22日、井上馨外相が5か国と条約改正に合意。しかし裁判に外国人判事を任用するなどの実質変わらない条約改正案の内容が公表されるとに反対運動が起こる。裏を返せば、まだ国としてなんの後ろ盾の力もない日本は条約改正したくてもできなかった。列強と対等に見られるため近代的な憲法が必要でした。
6月、伊藤博文ら「憲法草案」作り始める。
目指したものドイツ式立憲君主制。
伊藤以外の憲法草案のメンバー↓
井上毅(こわし・肥後)渡欧経験あり教育勅語草案にも参加。
伊藤巳代治(みよじ・肥前)憲法調査の為伊藤に随行。
金子堅太郎(筑前)岩倉使節団そのままハーバード卒。
8月、憲法草案完成、作った場所にちなみ「夏島草案」と呼ぶ。
9月、条約改正案に閣僚も反対し井上外相辞任せざる負えなくなった。
10月、条約改正案反対で民権運動が再燃。
12月、保安条例公布で民権運動派危険人物570人を東京から排除。
明治21年4月30日、憲法草案の審議の為、枢密院を設立。
内閣から独立した存在で直接天皇を補佐する諮問機関。初代枢密院議長に伊藤就任同時に総理辞任したため後任に黒田清隆(薩摩・幕末牛深へ来ていた)就任。
6月18日、枢密院憲法会議初日、伊藤は自分の考えを演説。
「ヨーロッパでは道徳的な基軸として宗教を持つが、我が国では宗教の力が弱く基軸とすべきは皇室あるのみ」と力説している。神道でもなく皇室だと言っているのは実質同じだと言ってもいいけどはっきり言うと皇室を中心とした皇室神道っていう分類になると思う。
10月、明治宮殿完成。(現在の皇居)表は和装、内は洋装。
11月、日墨(メキシコ)修好通商条約締結。初の完全対等条約。
明治22(1889)年2月11日、大日本帝国憲法発布。東アジア初近代憲法を持つ国になった。

出来たばかりの新しい皇居(明治宮殿で)発布。明治天皇から憲法を渡されている人は総理の黒田。

外務大臣を辞任した井上は黒田内閣になると農商務大臣へ復帰している。
大日本帝国憲法については大テーマなのでまた次の回へ。まだ国会開設までいけませんでしたねw
Posted by hirok○ at 03:53│Comments(0)
│明治~
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。