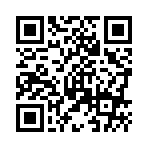2014年10月29日
その名は牛深御番所!
こんにちわ!
はじめましての人ははじめまして!
第一回ということでこのブログでの第一目標を書いておきます。
『牛深御番所の認識を高めること』です。
もちろん現時点では私も全く知識がありません。
私自身勉強していく過程を公開することによりご説明ができるかなと思っています。
牛深においてこの『牛深御番所』のことはほとんど知られておらず、なんとなく遠見番所は知られている感じは受けますが、それはその他の天草地域にも遠見番所がある為であるためだろうなと思っている。
その認識度合いからすると遠見番所の方が重要だから覚えられている?!と印象を受ける人が多いでしょう。ですがその内容を知っていくと、御番所と遠見番所は重要度が全く違い御番所はとても重要だったという事がわかる。おそらくその御番所が一部でも現存するなら文化庁指定史跡になることは間違いなかったでしょう。わかりやすく言うと国の重要文化財だってことです。
そしてその認識の低さの理由に旧牛深市にはいわゆる市の歴史を編纂した『牛深市史』が無かった事が大きいと思う。市民が自分の住んでいるところの歴史を気軽に学ぶことが出来なかったことは旧市の担当者だった方々もみなさん残念でならないと仰っている。
個人的には牛深といえば『御番所』ってなるぐらいの素材でもあると信じている。
昨年から天草検定が開催されていますが、この検定テキストには現在牛深御番所なんて言葉は一言も載っていない。こういうところにも載ることが当たり前になる未来を夢見て勉強して公開していきます。
なに分江戸時代のことになるので表現が難しく伝わりにくい事が多いと予想されます。できるだけわかりやすく書く予定ではありますが、わからねーよとか意味がわかんないなど気軽に言ってもらって構いません。
ご質問には私がわからなくても郷土史家の方々にお聞きして改めてご説明させていただこうと思っておりますので根気よく読んでいただけたらなぁと思っております。
それでは始まります。
*.♪★*・゜.♪★*・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.
天草初代代官鈴木重成は、江戸幕府による主導のもと異国船対策として遠見番制度を設けました。
(遠見番所のその細かい背景はまた別の機会に書きます、今回は触りだけに留めます)
寛永18年(西暦1641年、以降4桁の数字は西暦)富岡、大江崎、魚貫崎に遠見番所(見晴らしの良い所から海を監視するもの)が設置され、萬時3年(1660)に高浜村大野崎、亨保2年(1717)に崎津とともに増設されたものが牛深遠見番所です。
その遠見番所があった現遠見山(銀杏山)の中腹には中継地点として中番所がありました。現在中番所跡ということで展望できる建物がございますが正確にはその場所ではなかったとのことで、水道山から頂上へ向かう道路整備のためその場所は無くなってしまったとの事。(中番所についても後日詳細記事書きます)
そして寛政11年(1799)4月22日現在の船津地先(現在のAコープ、Aコープより以前は漁業組合)に長崎奉行直轄『牛深御番所』正式名が新設された。
まず第一回目なのでこの名称についてである。
歴史書や現在の歴史説明板には『牛深湊御番所』や『牛深湊見張御番所』などと表記されていたりします。海彩館での表記もそうなっている。これらは当時より牛深を単に牛深と言うより、港としての牛深が良く知られていたためわかりやすく唱えた愛称のようなものだっただろうとのこと。
ここでその時代の公式文書をお見せします。

この文書は俵物(今回省略これも後日記載します)に関する世話役への呼出状である。
いやぁ、それにしても文字が美しすぎる。芸術品として眺めたい古文書である。
黄色で囲った部分『牛深御番所』と書いてあるのがわかると思います。これが公式で使われていた名称です。
最後の個人名の世話役のところを見ても久玉村中原新吾と書いてあり、牛深が久玉村だったというのが改めて分かる面白い。関連→牛深第七景
享和2年(1802)にはその世話役が牛深村庄屋長岡惣左衛門嬉七郎と他の文章に見えている事により上の文章は御番所新設初期の頃のものと推定できる。
というところで第一回目は終わりにしたいと思います。いやぁやはり伝わりにくくなってますね。説明不足で申し訳ありません。少しずつ説明を増やしていきたいと思いますので次回もまたお付き合いくださいませ。
はじめましての人ははじめまして!
第一回ということでこのブログでの第一目標を書いておきます。
『牛深御番所の認識を高めること』です。
もちろん現時点では私も全く知識がありません。
私自身勉強していく過程を公開することによりご説明ができるかなと思っています。
牛深においてこの『牛深御番所』のことはほとんど知られておらず、なんとなく遠見番所は知られている感じは受けますが、それはその他の天草地域にも遠見番所がある為であるためだろうなと思っている。
その認識度合いからすると遠見番所の方が重要だから覚えられている?!と印象を受ける人が多いでしょう。ですがその内容を知っていくと、御番所と遠見番所は重要度が全く違い御番所はとても重要だったという事がわかる。おそらくその御番所が一部でも現存するなら文化庁指定史跡になることは間違いなかったでしょう。わかりやすく言うと国の重要文化財だってことです。
そしてその認識の低さの理由に旧牛深市にはいわゆる市の歴史を編纂した『牛深市史』が無かった事が大きいと思う。市民が自分の住んでいるところの歴史を気軽に学ぶことが出来なかったことは旧市の担当者だった方々もみなさん残念でならないと仰っている。
個人的には牛深といえば『御番所』ってなるぐらいの素材でもあると信じている。
昨年から天草検定が開催されていますが、この検定テキストには現在牛深御番所なんて言葉は一言も載っていない。こういうところにも載ることが当たり前になる未来を夢見て勉強して公開していきます。
なに分江戸時代のことになるので表現が難しく伝わりにくい事が多いと予想されます。できるだけわかりやすく書く予定ではありますが、わからねーよとか意味がわかんないなど気軽に言ってもらって構いません。
ご質問には私がわからなくても郷土史家の方々にお聞きして改めてご説明させていただこうと思っておりますので根気よく読んでいただけたらなぁと思っております。
それでは始まります。
*.♪★*・゜.♪★*・*♪*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.♪★*.♪★*・゜*.♪★*・゜・*♪*.
天草初代代官鈴木重成は、江戸幕府による主導のもと異国船対策として遠見番制度を設けました。
(遠見番所のその細かい背景はまた別の機会に書きます、今回は触りだけに留めます)
寛永18年(西暦1641年、以降4桁の数字は西暦)富岡、大江崎、魚貫崎に遠見番所(見晴らしの良い所から海を監視するもの)が設置され、萬時3年(1660)に高浜村大野崎、亨保2年(1717)に崎津とともに増設されたものが牛深遠見番所です。
その遠見番所があった現遠見山(銀杏山)の中腹には中継地点として中番所がありました。現在中番所跡ということで展望できる建物がございますが正確にはその場所ではなかったとのことで、水道山から頂上へ向かう道路整備のためその場所は無くなってしまったとの事。(中番所についても後日詳細記事書きます)
そして寛政11年(1799)4月22日現在の船津地先(現在のAコープ、Aコープより以前は漁業組合)に長崎奉行直轄『牛深御番所』正式名が新設された。
まず第一回目なのでこの名称についてである。
歴史書や現在の歴史説明板には『牛深湊御番所』や『牛深湊見張御番所』などと表記されていたりします。海彩館での表記もそうなっている。これらは当時より牛深を単に牛深と言うより、港としての牛深が良く知られていたためわかりやすく唱えた愛称のようなものだっただろうとのこと。
ここでその時代の公式文書をお見せします。

この文書は俵物(今回省略これも後日記載します)に関する世話役への呼出状である。
いやぁ、それにしても文字が美しすぎる。芸術品として眺めたい古文書である。
黄色で囲った部分『牛深御番所』と書いてあるのがわかると思います。これが公式で使われていた名称です。
最後の個人名の世話役のところを見ても久玉村中原新吾と書いてあり、牛深が久玉村だったというのが改めて分かる面白い。関連→牛深第七景
享和2年(1802)にはその世話役が牛深村庄屋長岡惣左衛門嬉七郎と他の文章に見えている事により上の文章は御番所新設初期の頃のものと推定できる。
というところで第一回目は終わりにしたいと思います。いやぁやはり伝わりにくくなってますね。説明不足で申し訳ありません。少しずつ説明を増やしていきたいと思いますので次回もまたお付き合いくださいませ。
この記事へのコメント
歴史をさかのぼって説明してもらうと、その時代の人々の様子が浮かんできます。
とても面白いですね。
連載を楽しみにしてます。
とても面白いですね。
連載を楽しみにしてます。
Posted by やっぱり太陽 at 2014年10月29日 10:33
》やっぱり太陽さん
私も勉強しながらですので時間がかかると思いますが末永くよろしくお願いいたします。
ほんとに面白いんです、ぜひみなさんにお伝えしたくて。
私も勉強しながらですので時間がかかると思いますが末永くよろしくお願いいたします。
ほんとに面白いんです、ぜひみなさんにお伝えしたくて。
Posted by hirok at 2014年11月16日 00:21
at 2014年11月16日 00:21
 at 2014年11月16日 00:21
at 2014年11月16日 00:21※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。